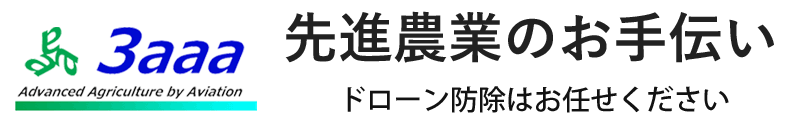薬剤の規制は?
防除に使用する薬剤(農薬)は、農薬取締法、環境保護法、一部毒劇物取締法によって規制がかけられています。 それは、まさに毒にも薬にもなるからであり、決められた用方通りに使用することが必須条件です。
農薬の残留はだいじょうぶ?
食品や環境の安全のためにポジティブ制度がとりいれられたりと残留基準は年々厳しくなっていますが、登録農薬であれば決められた施用法を厳守して正しく使用することでクリアできるものでもあります。
薬剤はその薬効だけではなく、コスト面も考える必要があるので、防除で散布する際は防除対象への適合や希釈倍率、散布量、施用時期など、定められた内容を厳守した上で適時防除による薬剤の使用の効率面を考えることがとても重要です。
農薬が環境に与える影響について
環境への影響を低減するには、定められた条件に沿って定められた用法、例えば希釈倍率、散布量、散布回数、などを厳密に守り、周囲への影響評価、例えば水生生物、みつばちや蚕などの感受性の可能性などを判断したうえで所望の防除対象への効果が高い薬剤を選定することが出発点になります。
稲につく害虫はウンカ類やカメムシ、コブノメイガ、イナゴなど多々ありますが、近年の農薬は昔のように根こそぎ駆除するようなものではなく、駆除対象を絞って効果が出るようになっており、1種類で全てに効果があるものはありません。 また、同一種であっても、成虫には効くが幼虫、卵には効かないなどということも普通にありますし、さらに言えば、薬剤が効かなくなる薬剤耐性を持った個体の発生などもあります。 したがって、防除対象とその適期を見定めて最適かつ効率的な薬剤の選択を行ったうえで、先述の用法を厳密に守る事が必要です。
各薬剤には化学品に起因する予見可能なリスクについて周知し、化学品に関わる人の健康及び環境に対する災害・事故を防ぐことを最大の目的とするSDS(安全データシート)が公開されています。
記載された予見可能なリスクに対して対策をしっかり取ることで健康及び環境に対する災害・事故を防ぐことができるということになります。
3aaaは防除業者ですが
3aaaは防除を生業にしているのですが、その目的は薬剤の散布ではありません。
矛盾するようですが、最適解によるリスク低減とお客様の利益の向上を旨としているので、病害虫のリスクが低い年はお受けする作業は当然少なくなります。(ルーティーン散布はお受けしておりません)
このカテゴリーでは、農薬指導士視点で最適解を求める試行錯誤の中から得た情報や、お客様のご経験などを加えた知見を投稿していきます。