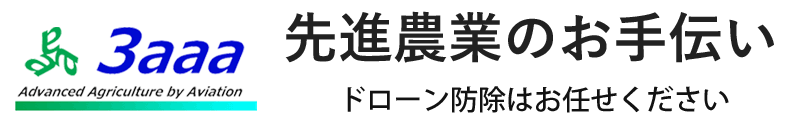ドローンという言葉は、もうすっかり一般的になってきましたが、そんなドローンについての雑感をざっくりとまとめてみました。
ドローン普及の背景
特段の訓練無しでも飛んでしまい、それにカメラがプラスされたことでブレークしたドローン。
製作の過程や、調整したり飛ばすことそのものが目的だったラジコンとは違い、その飛行の容易さによりガジェットとしての付加価値を持ったことで一挙に市場が広がりました。
それを支える LiPo(リチウムポリマー)バッテリー、GPSや姿勢を制御するジャイロ、気圧、地磁気などを検知するセンサー情報をもとに機体を制御するフライトコントローラーが小型高性能になったことで誰でも飛ばせる機体になったことが背景としては大きいですね。
ドローンが認知され始めたとき、ラジコンを長年やってきたものからすると「こんなん誰が飛ばすと?」とかいって笑ってたんですよ。。。。
空モノラジコンに電動化の波が訪れたのは、NiMH、NiCd電池に代わってLiPo電池が登場したときからです。 そのころのLiPo電池は神経質でちょっとしたことですぐ燃えて危ないがパワーの出る電池という代物でした。 マニアの方々がバランス充電やセルの管理を試行錯誤しながら確立していったことによりRC電動機というジャンルが確立されることになります。
ちょうどその頃、DJIがバラックのフレームに組んだような4ローター、6ロータの機体を販売していました。 先にも言ったとおり、へぇ~と言っていたものが今では皆さんご承知のとおりになるなんて。。。。。。。。
本当に未来を予測することは難しいです。
ドローンを開発したのはあの会社
今では中国のDJIやフランスのParrotなどに席巻されていますが、いわゆる4ローターのマルチコプター型を1989年世界で初めて発売したのは日本のキーエンスです。
当時はバッテリーがNiMHだったりGPSなども搭載していなかったため、結構飛ばすのは難しかったようですが、あのキーエンスがその将来性を見いだせなかったことは残念ほかなりません。
やはり、未来を予測するのは難しいことなんですね。
日本の業界の状況は?
日本には、プロポのFUTABAやかつてラジコンヘリコプターで世界を席巻したヒロボーなど世界に誇るメーカーがたくさんあったのですがドローンの普及に反して業界は衰退の一途をたどっています。
今般の規制でラジコンはオワコンとなりつつあり、業界の衰退はさらに加速されるでしょう。
政府が国産ドローンの開発を支援するという発表をしましたが、ラジコン業界で培われたリソースはおそらく役に立てられないでしょう。 フライトコントローラーそのものを構成する個々のデバイスでは日本の存在感はまだまだありますが、ここでもアプリケーションとしてまとめる事ができないところに日本の弱点があらわになっていますね。
しかし、ヤマハなどの大型の散布ヘリはしっかり根付いていますし、F3A,F3Cといったラジコン飛行機やヘリの国際大会では多くの世界チャンピオンを輩出してきた日本です。そこを頂点とする裾野は広がっているのでオペレーションの分野では多くの蓄積が応用できるはずです。
日本は巻き返せるか
私が飛ばしているドローンですが、組み立ては日本、プロポがFUTABAである以外はフライトコントローラー、モーター、バッテリー、機体、補機類。。。。。は、まるっと中国製です。
最後の砦がプロポでしたが、ここ最近着実に中国製が勢力を伸ばしています。
インターネットに接続され、マップ上で飛行ルートを計算することで自動飛行を可能とするアプリをアンドロイドベースのタブレットに載せ、プロポと統合するものが出てきてからこの流れが顕著です。

フライトコントローラーの制御アルゴリズムで水を開けられていて個々の要素をまとめることが苦手な日本の現状ではなかなか厳しいとは思いますが、なんとか逆転の道を開いてもらいたいものです。
ドローンの弱点とは
とりあえずだれでも安定して飛ばすことができるドローンですが、GPSを始めとする様々な情報を演算処理し、電子的に制御することで安定を保っています。
極端に言うと、手のひらの上に棒を立てて、倒れないようにバランスを取ってくれているイメージです。
稀ではありますが、ローターのうち一つでも停止するようなことになれば、墜落はまず避けられません。

シングルローターのいわゆるヘリでは、条件によりますがオートローテーションで操作する余地がのこされていますがドローンはこれがありません。
こういった事が起こる原因として、フライトコントローラーの不具合、ケーブル類の接触不良、ノイズ、ローターの折損、モーターのロックなどがありますが、ほぼ電気的な不具合です。
機械的な不具合は音、振動である程度予見でき、その後の点検である程度防ぐことはできるのですが、電気的な不具合は兆候を掴むのが難しく、突発的に発生することがほとんどなので、そうなる可能性を常に頭に入れた上で操縦することが必要です。
また、GPSの衛星補足数が少なくなったり、高圧線や鉄板などの磁気により地磁気センサーが誤検知することで不安定になる場合があります。 具体的には、停止位置がふらついたり流れたりといった症状が出たりします。また気圧高度計(バロメーター)の不具合で高度が乱高下する場合もあリます。
こういった場合は、ATTモードと言ってマニュアルで操縦することで回避します。 つまり、ドローンの自動制御に頼らなくても操縦できる技量が必要ということです。
ドローンを飛行させるということの本質は、めちゃめちゃ不安定なものを制御で安定させて飛行しているということをしっかり認識した上で常にリスクへの対応ができる状態にしておくということだと思います。